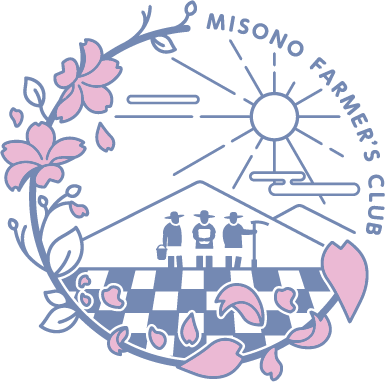2025年9月22日(月)
ハロウィンシーズンに知っておきたい代表的なカボチャ品種まとめ
実は種類もレシピもいっぱい!栽培方法も
ハロウィンが近づくと話題になるカボチャですが、一口にカボチャと言っても実は非常に多くの品種があります。形や色、大きさもさまざまで、食用としての味わいや適した料理、栽培のしやすさなど品種ごとに特徴が異なります。
カボチャは大きく西洋カボチャ・日本カボチャ・ペポカボチャの3系統に分類され、普段スーパーで見かける濃い緑色の栗カボチャは甘みが強い西洋カボチャに属します 。一方、京野菜など伝統品種の日本カボチャは水分が多くねっとりした食感で甘みは控えめですが煮物向きなのが特徴です 。
そしてペポカボチャにはユニークな形の観賞用カボチャが多く含まれ、ハロウィンで思い浮かべるオレンジ色の大きなカボチャのほとんどはこの仲間です 。この記事では一般消費者や家庭菜園ユーザーに向けて、ハロウィンシーズンにぜひ知っておきたい代表的なカボチャ品種を10種類以上紹介します。
それぞれの概要(形や色、由来など)、食用の場合の味の特徴とおすすめレシピ、栽培方法(適した気候や育て方のポイント)について詳しく解説します。記事の最後には、紹介した各カボチャの「食べるのに向いている度」と「ハロウィン飾りに向いている度」を☆5段階評価した一覧表も掲載しますので、用途に合わせたカボチャ選びの参考にしてください。
えびすかぼちゃ(黒皮栗かぼちゃ)

えびすかぼちゃは、日本で最も広く栽培され流通している代表的な西洋カボチャ品種です 。濃い緑色の硬い皮に薄い緑色の斑点模様(ちらし斑)が入った扁平な球形をしており、重さは1.7~1.9kgほどになります 。
果肉は濃いオレンジ色で厚みがあり、適度にホクホク感としっとり感を併せ持った上品な甘さが特徴です 。揚げ物との相性が良く、天ぷらや素揚げ、コロッケなどにするとホクホク感と甘みが引き立ちます 。煮崩れしにくいため煮物やスープにも向いており、カボチャサラダなど幅広い料理に使える万能選手として長年親しまれています 。
栽培のポイント: えびすかぼちゃは環境適応力が高く着果も良いため、多収で育てやすく、初心者からプロまで安心して栽培できる人気品種です 。発芽適温は28~30℃と高めですが、生育適温は15~25℃と比較的幅広く、日本各地で栽培可能です。
種まきは春(4~5月)が適期で、ポット播きまたは直播きで育苗します 。日当たりと排水の良い場所を好み、高温期によく育つ反面、肥料過多にするとツルボケしやすいので控えめの施肥にします 。
本葉が4~5枚になったら畑か大型プランター(横60cm以上)に定植し、1株あたり1~2㎡ほどのツルを伸ばすスペースを確保しましょう 。子ヅルの整枝や受粉の補助(人工授粉)を行い、受粉後約45~50日が収穫の目安です 。収穫後1週間~1ヶ月ほど風通しの良い日陰で追熟させると甘みが増し、美味しくなります 。
くりゆたか

くりゆたかは、西洋カボチャの一品種で、その名の通り栗のようにおいしい粉質のカボチャです。果重約1.8~2.0kgになる大型種で、果皮はやや濃い緑色、形は腰高の扁円形をしています 。果肉がぎっしりと詰まっており、加熱するとホクホクと粉を吹くほどの食感で甘みも非常に強く出るのが魅力です 。
シンプルに煮物にすると素材の甘さを存分に味わえ、マッシュしてサラダにしても濃厚なおいしさを楽しめます 。その名の「ゆたか」が示すように収量性も高く、家庭菜園でも人気の品種です。
栽培のポイント: くりゆたかは基本的な育て方は他の西洋カボチャと同様ですが、大玉になるぶん十分な肥料と水分を好みます。栽培適温はえびすかぼちゃ同様で、暖かい地域から寒冷地まで幅広く適応します。
雌花着果後は1株あたり2~3果を目安に育てると、しっかりと大きく育ち品質も安定します(着果数を増やし過ぎると甘味が乗りにくくなるためです)。追肥を適宜与えつつツルを整え、雑草と病害虫(うどんこ病など)に注意しながら管理しましょう。
果実が熟すとヘタ周りがコルク化し、叩いて澄んだ音がするようになります。その頃(受粉後50日前後)が収穫適期です。収穫後は風通しの良い場所で1ヶ月ほど追熟させるとさらに甘みが増します 。
坊ちゃんかぼちゃ

坊ちゃんかぼちゃは、重さ500g前後しかない手のひらサイズがかわいらしいミニカボチャです 。未熟なうちに収穫したものではなく、このサイズで完熟する品種で、濃い緑色の丸い実をつけます。
見た目はミニチュア版の栗カボチャといった感じで、肉質や風味も一般的な栗カボチャによく似ています 。小さいながらも甘みが強くホクホクとした食感が楽しめ、栄養価も高くβカロテンなどが豊富です 。
丸ごと調理しやすいサイズ感を活かし、中をくり抜いてグラタンやプリンの容器に使うなど、見た目も可愛い料理にもよく利用されています 。実はこの坊ちゃんには皮の色違いで「赤い坊ちゃん」(オレンジ色の皮)と「白い坊ちゃん」(白い皮)という品種もあり、赤い坊ちゃんは果肉がややねっとり、白い坊ちゃんはよりホクホクした食感になるといいます 。
栽培のポイント: 坊ちゃんかぼちゃは省スペースで栽培でき、家庭菜園でも人気のミニ品種です。ツルはそれほど長く伸びず管理しやすいため、支柱を立てた立体栽培やプランター栽培にも向いています。
基本的な育て方は他のカボチャと同様ですが、果実が小さいぶん着果数が多くなりがちです。露地栽培では1株から5~6個前後の実をつけます 。株が弱らないよう、生育状況に応じてある程度摘果し、株元近くの果実を優先的に残すとよいでしょう 。小さい果実は地面と接すると傷みやすいため、敷き藁やマットを敷いて予防します。
収穫時期は7~9月で、熟した坊ちゃんはヘタが木質化し栓が抜けたようになるので見極めましょう。収穫後は他のカボチャ同様、しばらく常温保存すると甘みが増します 。
バターナッツかぼちゃ

バターナッツかぼちゃは、ひょうたん型の細長い見た目がユニークなカボチャです 。北アメリカから南アメリカの砂漠地帯が原産とされ、日本には比較的新しく入ってきました 。近年ではホームセンターなどで種や苗が販売されており、家庭菜園でも人気が高まっています 。外皮は黄土色〜淡いベージュ色で一見カボチャらしくない色合いですが、半分に割ると中から鮮やかなオレンジ色の果肉が現れます 。名前の通り「バターのようになめらかでナッツのように甘い」風味が特徴で、繊維質が少なく加熱するととろりとなめらかな舌触りになります 。ポタージュやスープ、ピューレにするとクリーミーでコクのある味わいを楽しめるため特におすすめです 。もちろん、ローストしてグリル野菜にしたり、角切りにして煮込み料理やカレーに入れるなど幅広いレシピに活用できます。
栽培のポイント: バターナッツは南米原産らしく暑さに強い一方で、低温にはやや弱い傾向があります。発芽適温は高めなので、十分暖かくなってから種まき・定植を行いましょう。日本では6~7月頃までに種をまき、9~10月頃の収穫を目指す作型が一般的です。果実が縦長で地面に接しやすいため、敷き藁や支柱利用で実が地面に直接触れないようにすると形が綺麗に育ちます。果皮が完全にベージュ色になり、表面にうっすら粉を吹いたようになったら収穫適期です。追熟期間をとらず収穫後すぐに食べても甘みがあるのが特徴ですが、風通しの良い場所で数週間寝かせるとさらに甘さが増す場合もあります。なお、ツルボケ(ツルばかり茂り実つきが悪くなる現象)しやすいので肥料の与えすぎに注意し、必要に応じて摘芯して子ヅル・孫ヅルに受粉させると着果が安定します 。
九重栗かぼちゃ

九重栗(くじゅうくり)かぼちゃは、その名の通り栗のように甘くホクホクした西洋カボチャで、「黒皮栗かぼちゃ」の品種群の一つです 。果皮は濃緑色で薄い縦縞模様が入り、やや腰高でハート形にも見えるユニークな形をしています 。皮が薄く柔らかいので包丁でカットしやすく、調理の際は皮ごと食べることも可能です 。果肉は鮮やかな濃黄色で密に詰まっており、加熱すると粉を吹くほどホクホクとした食感になる非常に粉質な品種です 。甘みも強く、煮物やグラタン、サラダなどさまざまな料理で活躍する万能カボチャと言えるでしょう 。スイーツ作りにも向いており、パンプキンパイやプリンの材料に使うと上品な甘さが引き立ちます。
栽培のポイント: 九重栗かぼちゃは家庭菜園でも育てやすい品種として人気があります 。一般的な西洋カボチャと同様に育てられ、収穫時期は早いものでは6月下旬から始まり、盛期は7~8月頃です 。1株から複数の果実が収穫できますが、大きく育てたい場合は着果数を2~3個程度に制限すると良いでしょう。完熟のサインは果柄(ヘタ)が茶色く木質化し、皮にツヤが無くなる頃です。実が粉質でホクホクな分、煮込み料理では煮崩れしやすいので、栽培中の追肥で窒素を多めに与えるなどしっとり感を残す工夫をすると調理しやすい固さになります 。貯蔵性もある程度あり、採れたてよりも数週間追熟させた方が甘味が増す点は他の栗カボチャと共通です。
ロロンかぼちゃ

ロロンかぼちゃは、ラグビーボールのような細長い楕円形の果実と約2kgに達する大玉サイズが特徴の西洋カボチャです 。濃緑色の皮に独特のまだら模様(ちらし斑)が入り、果肉はキメが細かく滑らかな舌触りをしています 。
上品な甘さとホクホクした食感を併せ持ち、スープやポタージュにするとクリーミーでコクのある味わいになります。また、煮物やコロッケはもちろん、ペースト状にしてプリンやケーキなどスイーツに利用するのにも適しています 。
名前の由来は「もっと消費者にカボチャを食べてほしい」という育成者のロマンと、栗(マロン)のように甘い食味を掛け合わせて「ロロン」と名付けられました 。タキイ種苗が開発し2009年に販売開始された比較的新しい品種で、生産量はまだ多くありませんが、その美味しさから徐々に注目を集めています 。
栽培のポイント: ロロンかぼちゃはツルが勢いよく伸び、広い畑でのびのび育てると大きな実をつけます。省力型で側枝(子ヅル)が少ない性質を持つため、比較的手間がかからず栽培できる点も魅力です 。
基本的な栽培条件は他の西洋カボチャと同じですが、大玉ゆえに肥料切れを起こさないよう注意します 。適期に追肥を与え、果実肥大期には水分もしっかり供給しましょう。
名前に違わず完熟収穫したロロンの甘さは格別なので、実が十分成熟するまで(開花後50日程度)じっくり育ててください。完熟すると果皮のまだら模様のコントラストがはっきりし、ヘタ部分がコルク状になります。収穫後は1ヶ月ほど涼しい場所で保管し追熟させると、より甘みが増して美味しくなります。
そうめんかぼちゃ(金糸瓜)

そうめんかぼちゃ(金糸瓜〈きんしうり〉)は、ペポカボチャに分類されるユニークな品種で、別名を「そうめん瓜」ともいいます 。一見ウリのような細長い楕円形で、果皮は淡い黄色~クリーム色です。
最大の特徴は加熱したときに果肉が糸状にほぐれることで、ゆでた果肉をほぐすとまるで素麺のようなシャキシャキとした細い繊維になります 。この性質を活かし、酢の物や三杯酢あえ、おひたし、サラダなどさっぱりした料理に使われるほか、めんつゆをかけて本物のそうめんのように食べるのもおすすめです 。
味自体は淡泊でクセがないため、和え衣やドレッシングとの相性が良く、食感を楽しむ食材として古くから親しまれてきました。
栽培のポイント: そうめんかぼちゃは日本では主に西日本~中部地方で古くから栽培されてきた伝統野菜です。
ウリ科ですが高温にも比較的強く、家庭菜園でも育てやすい部類に入ります。種まきから収穫まで生育が早く、受粉後約40~45日で収穫できます 。
果皮が黄味がかり、指で押して少し弾力を感じる程度になったら収穫のタイミングです。収穫した実は新鮮なうちに食べるのがおいしく、追熟による甘み向上は見込めないので採れたら早めに調理しましょう 。
果肉をそうめん状にするには、輪切りにして種を除き、沸騰した湯で10~15分ほどゆでます。その後水にさらしながら指やフォークでほぐすと金糸のような繊維が現れます。柔らかくなりすぎないよう茹ですぎに注意し、シャキシャキ感が残る状態で引き上げるのがポイントです。収穫期は夏(7~9月)で、暑い時期にさっぱり食べられる涼味野菜として重宝します。
コリンキー

コリンキーは、生で食べられる珍しいサラダカボチャとして注目されている品種です 。オーストラリア原産のカボチャと日本のカボチャを掛け合わせて開発された経緯があり、2000年代に登場しました 。果皮は鮮やかなレモンイエローで艶があり、見た目にも美しいカボチャです 。
一般的なカボチャと違って皮がとても柔らかく、包丁で切りやすいので調理も簡単です 。未熟な若採り状態で収穫するため、皮ごと生で食べることができ、シャキシャキ・コリコリとした独特の歯応えが楽しめます 。
クセがなく瑞々しい味わいで、食感はズッキーニやキュウリにも似ているため、サラダや浅漬けにするとおいしくいただけます 。薄くスライスしてサラダの彩りにしたり、千切りにしてコールスロー風にするのもおすすめです。加熱調理も可能で、炒め物やスープに入れてもくたくたになりすぎず食感が残ります。
栽培のポイント: コリンキーはペポ種に属し、ズッキーニと似た感覚で育てることができます。発芽・生育適温は20~30℃程度で、初夏から夏にかけてどんどん成長します。人工授粉後、着果からわずか20~30日程度の若い段階で収穫できるのが特徴で、栽培期間が短いのも利点です。
開花後約3週間、直径10~15cmほどに実が大きくなったら収穫適期としましょう。それ以上熟すと果皮が固くなり生食に適さなくなるため、早めの収穫を心掛けます。
次々と実をつけるため、定期的に収穫して株の負担を軽減すると長く収穫を楽しめます。ウリ科につきもののウリハムシ被害やべと病・うどんこ病には注意し、防虫ネットや薬剤で予防します。プランターでも育てやすいですが、ツルが伸びたらこまめに誘引して絡まりを防ぎましょう。
栽培中は開花した花も食用に利用でき、若い葉や芽も食べられることがありますので、家庭菜園ならではの楽しみ方もできます。
雪化粧かぼちゃ

雪化粧(ゆきげしょう)かぼちゃは、その名の通り灰白色の粉をふいたような外皮が特徴的な西洋カボチャの品種です。見た目は白皮ですが、うっすら薄緑がかったグレーにも見えるユニークな色合いで、果実はずっしり2.3kg前後になる大型種です 。
果肉は淡い黄色で、茹でると鮮やかな黄色に発色します 。極めて粉質でホクホク感が強く、甘みも濃厚なため「栗より甘い」と評されるほどの食味を持ちます 。
煮物や天ぷらにしても煮崩れしにくく、調理後の形が崩れにくい安定した食感も魅力です 。皮はやや固めですが、加熱すればホロっと柔らかくなり、口当たりの邪魔をしません 。収穫直後よりも長期保存で甘みが増す品種として知られ、適切に追熟させれば3ヶ月後でも美味しさが持続する高い貯蔵性を誇ります 。
栽培のポイント: 雪化粧かぼちゃは寒冷地での栽培にも適しており、北海道や東北・新潟などでも盛んに作られています 。
暑さにも寒さにも比較的強い品種ですが、完熟までに日数がかかるため、生育期間を長めに確保できるよう早播き(4月頃からの育苗)を心がけます。
株当たりの収穫数は一般的に2~4個程度に制限し、一つ一つの実を充実させる一果取(いっかど)栽培を行うこともあります 。
その場合、メロン栽培のように贅沢に栄養を注ぎこむことで糖度がさらに上がり、美味しいカボチャになります 。完熟収穫した雪化粧は、涼しい場所で1~2ヶ月追熟させるとデンプンが糖に変わり甘さが増します 。
10月頃にはホクホク感が強くなり、11月以降は熟成が進んでねっとり感も出てくるなど、時間経過による味と食感の変化も楽しめるカボチャです 。
宿儺かぼちゃ

宿儺(すくな)かぼちゃは、岐阜県高山市丹生川町を原産とする伝統野菜で、独特の細長い形状をした日本カボチャの一種です 。見た目はヘチマやズッキーニにも似た細長いひょうたん型で、長さ50cm前後にも達します。皮は薄い灰緑色でつるりと滑らか、果肉は濃い黄色をしており、強い甘みとホクホクした食感が楽しめます 。一般的な日本カボチャ(黒皮や京野菜系)はねっとり系が多い中、宿儺かぼちゃは栗カボチャに負けないホクホク感があるのが特徴です。皮が薄く調理しやすいため、包丁で切り分けやすく、煮物や天ぷらはもちろんポタージュやプリンなどスイーツにも利用しやすい万能選手です 。
栽培のポイント: 宿儺かぼちゃは古くから飛騨地方で自家用に細々と作られてきた品種でしたが、平成13年(2001年)に「宿儺かぼちゃ」として正式に名前が付けられブランド化されました 。それ以降、全国的にも知られるようになり種苗会社から種も販売されています。栽培そのものは一般的なカボチャと同様ですが、長形の実のため棚仕立てや吊り栽培で育てると真っ直ぐ形良く育ちます。果実が大きく長くなる分、1株あたりの着果数は抑えめにし、十分に肥大させましょう。完熟のタイミングは皮の色が完全に薄灰緑からベージュがかった色に変わり、ヘタが枯れてコルク状になった頃です。収穫後しばらく追熟させることで甘みがさらに増します。宿儺かぼちゃは日本カボチャ系なので、収穫直後でも甘さは控えめでねっとり、貯蔵熟成することで甘みが強まる傾向があります 。数ヶ月保存しても味が落ちにくく、冬まで美味しく食べられるのも利点です。
打木赤皮甘栗かぼちゃ

打木赤皮甘栗(うつぎあかかわあまぐり)かぼちゃは、石川県金沢市の伝統野菜「加賀野菜」に指定されている西洋カボチャ品種です 。
黒緑色が多い栗カボチャの中で、打木赤皮甘栗は名前の通り鮮やかな赤みがかったオレンジ色の皮が目を引きます。形は丸みを帯びていますが、ヘタが少し突き出しており、まるで玉ねぎのようなユニークなシルエットです。
皮が薄く柔らかいため、剥かずにそのまま調理して食べられ、調理後も皮の色を生かして鮮やかな仕上がりになります。ただし「栗カボチャ」という名前とは裏腹に、果肉はホクホクというよりむしろねっとり系で滑らかです 。優しい甘さがあり、煮汁とのなじみが良いので日本料理の炊き合わせなど煮物にぴったりです 。煮崩れもしにくく、盛り付けたときに橙色の皮が美しく映えます 。
この品種は昭和初期に福島県で作られていた赤皮栗カボチャを金沢の農家が導入し改良したもので、戦後しばらくは広く人気を集めましたが、黒皮栗カボチャ(えびす系)の台頭で一時生産が減った経緯があります 。近年になって伝統野菜が見直され、再び注目されるようになっています 。
栽培のポイント: 打木赤皮甘栗かぼちゃは西洋カボチャに属しますが、比較的高温多湿に弱く、乾燥した環境を好む傾向があります。
栽培自体は基本的に栗かぼちゃ型と同様ですが、つる枯病やうどんこ病に注意して風通し良く仕立てることが重要です。発芽から開花までは旺盛にツルを伸ばし、1株あたり2~3個程度の着果に絞って育てるとしっかりした実が得られます。果皮がオレンジ色から少しくすんだ朱色になり、ヘタが木質化してきたら収穫適期です。
追熟させると甘みが増しますが、長期間の保存性はえびす系ほど高くないため、早めに消費するのがおすすめです。皮が薄く傷つきやすいので、収穫後の取り扱いも丁寧に行いましょう。もし傷がついた場合でも、すぐ調理すれば問題なくおいしく食べられます。栗カボチャと比べ水分が多くねっとりした食感なので、ポタージュやプリンなど滑らかさを活かす料理にも適しています。
ハロウィンパンプキン(観賞用オレンジかぼちゃ)

ハロウィンのジャック・オー・ランタン作りに使われるオレンジ色の大玉かぼちゃも、忘れてはならない品種です。日本では特定の品種名より「ハロウィンかぼちゃ」「観賞用パンプキン」といった呼び方で流通することが多いですが、海外ではベビーパム (Baby Pam) やコネチカット・フィールド種などランタン向けの中~大型品種がいくつも存在します 。
一般的なハロウィンカボチャは直径30~50cmほどにもなるペポカボチャで、果皮は明るいオレンジ一色、表面が比較的なめらかで凹凸が少ないため**カービング(彫刻)**がしやすくなっています 。
果肉は薄く中は空洞が大きい構造で、ナイフで目や口をくり抜いてランタンを作るのに適した形状です 。日本では食用カボチャほどは出回りませんが、ホームセンターの種苗コーナーなどで種や苗が手に入ることがあります 。家庭菜園で育てて自家製ジャック・オー・ランタンを作るのも楽しいでしょう。
食味と利用: ハロウィン用の観賞かぼちゃは食べられないことはないものの、甘みが少なく水っぽい品種がほとんどです 。
実際、世界一巨大になる品種として有名なアトランティックジャイアントも数百キロのサイズに育ちますが、味は淡白で主に観賞専用です 。
そのため、大きく育てたハロウィンかぼちゃは基本的にジャック・オー・ランタンとして飾りに用いられます 。もっとも、適切に育てたオレンジかぼちゃの中には可食性がある程度高いものもあり、実際にスープやパイに利用されることもあります (※食用品種のシュガーパイなどは別途存在し、同じオレンジ色でもこちらは甘みがあります)。
とはいえ一般的には、ハロウィン当日に観賞用として楽しんだ後はコンポストにしたり、動物の餌にするケースが多いようです。栄養価自体は他のカボチャと大差ないため、味にこだわらなければポタージュやジャムに再利用することもできます。
栽培のポイント: 観賞用かぼちゃも基本的な育て方は他のカボチャと同様ですが、より大きさを重視する場合は栽培方法も特殊になります。特に巨大カボチャコンテストに挑戦する場合、1株から1玉だけを残して他は全て摘果し、株のエネルギーを集中させて超大玉を育てる「一果どり」が行われます 。
また、果実が地面と接する部分が腐りやすいため座布団や板を敷いて保護します 。通常サイズ(直径20~30cm程度)のハロウィンカボチャなら、家庭菜園でも2~3株育てれば秋には十分な数のランタン用かぼちゃを収穫できます。
繁茂したツルの中からオレンジ色の実がゴロゴロと顔を出す様子はとても楽しく、園芸ファンには人気のイベント栽培です。夏場にしっかり水と肥料を与えて大きく育て、果皮が鮮やかなオレンジ色になりヘタが枯れてきたら収穫適期です。
収穫後は風通しの良い日陰で1~2週間乾燥させて皮を硬化させると日持ちが良くなり、カービングもしやすくなります。ハロウィンまで長期保存する際は腐敗に注意し、涼しい場所で保管しましょう。
以上、代表的なカボチャの品種についてその特徴と楽しみ方、育て方を紹介しました。普段のお料理に使いやすい定番の栗かぼちゃから、サラダで生食できる変わり種、ハロウィンを盛り上げる観賞用かぼちゃまで、多種多様なカボチャが存在しています。
それぞれの個性を知ることで、「食べる楽しみ」と「飾る楽しみ」の両方が広がるでしょう。今年の秋はぜひ色々なカボチャを手に取って、味わってみたり飾ってみたりしてください。
最後に、各品種について「食べるのに向いている度」と「ハロウィンの飾りに向いている度」を☆5段階で評価した一覧表を掲載します。品種選びの参考にご活用ください。
| 品種 | 食用向き (味・調理適性) | ハロウィン飾り向き (形・映え) |
|---|---|---|
| えびすかぼちゃ 定番 | 5/5 | 2/5 |
| くりゆたか ホクホク | 5/5 | 2/5 |
| 坊ちゃんかぼちゃ ミニ | 5/5 | 3/5 |
| バターナッツ | 4/5 | 2/5 |
| 九重栗かぼちゃ | 5/5 | 1/5 |
| ロロンかぼちゃ | 4/5 | 2/5 |
| そうめんかぼちゃ(金糸瓜) | 3/5 | 1/5 |
| コリンキー 生食 | 4/5 | 2/5 |
| 雪化粧かぼちゃ | 5/5 | 3/5 |
| 宿儺かぼちゃ | 4/5 | 2/5 |
| 打木赤皮甘栗 | 4/5 | 3/5 |
| ハロウィンパンプキン | 2/5 | 5/5 |
表は横にスワイプできます。星は満点5。食用は味・調理適性、飾りは形・色・映え基準でスコア化。